コンポストのネズミ対策!【底に金網を敷く】効果的な予防と管理方法で快適な堆肥作りを実現

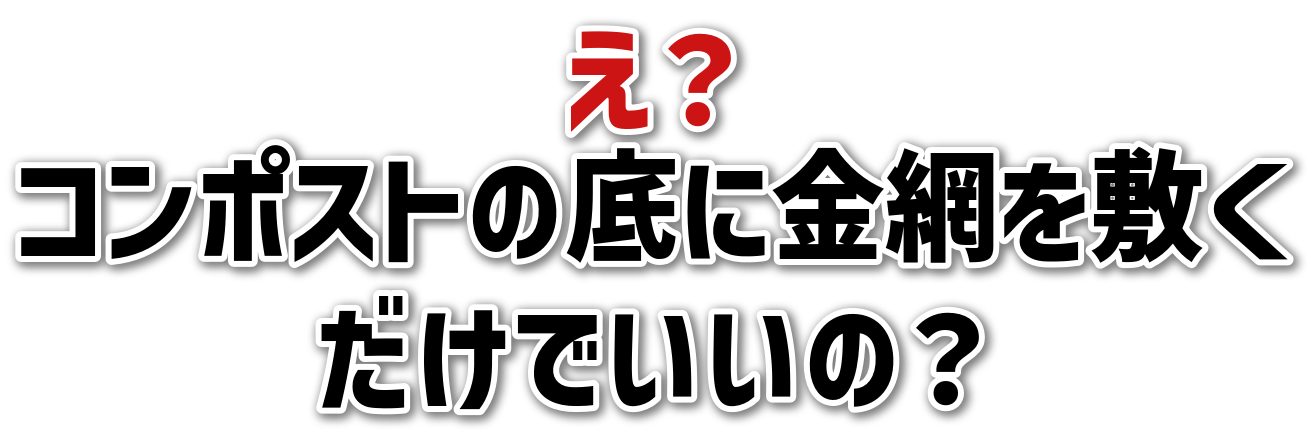
【この記事に書かれてあること】
庭いっぱいの野菜を夢見て始めたコンポスト作り。- コンポストに金網を敷くことでネズミ侵入を防止
- 堆肥の適切な温度管理がネズミ対策の鍵
- コンポストの設置場所と周辺環境の整備が重要
- 天然素材を活用した意外なネズミ対策法
- 堆肥化を成功させる10の裏技でネズミを撃退
でも、気づけばネズミの楽園に…。
そんな悩みを抱える方、必見です!
本記事では、コンポストのネズミ対策の決め手となる底部への金網設置をはじめ、驚きの裏技を10個ご紹介します。
ミントの香りやニンニクの皮など、身近な素材を活用した方法も満載。
これで、あなたのコンポストはネズミ知らずの堆肥工場に生まれ変わります。
さあ、豊かな土づくりの第一歩、一緒に踏み出しましょう!
【もくじ】
コンポストのネズミ被害!堆肥化に潜む落とし穴

ネズミが堆肥場に集まる3つの理由「餌・暖かさ・隠れ場所」
堆肥場はネズミにとって天国のような場所なんです。なぜネズミがこんなにも堆肥場を好むのか、その3つの理由を見てみましょう。
まず1つ目は「餌」です。
堆肥場には食べ物の残りカスがたくさんあります。
野菜くずや果物の皮など、ネズミにとってはごちそうがいっぱい。
「わーい、今日のご飯はなんだろう?」とネズミは喜んでやってくるわけです。
2つ目は「暖かさ」。
堆肥が発酵する過程で熱が出るため、堆肥場はポカポカと暖かいんです。
寒い季節には特に魅力的。
「ここなら寒い夜も快適に過ごせるぞ」とネズミは考えます。
3つ目は「隠れ場所」。
堆肥の山はネズミにとって絶好の隠れ家になります。
外敵から身を守り、子育てもできる安全な場所なんです。
これら3つの条件が揃っているため、ネズミにとって堆肥場は「住み心地バツグン!」の場所になってしまうのです。
でも、こんなにネズミが集まっては困りますよね。
- 餌が豊富にある
- 暖かい環境が整っている
- 安全な隠れ場所になる
「よし、ネズミさんたちにはお引っ越しをしてもらおう!」そんな気持ちで対策を考えていきましょう。
堆肥の種類による「ネズミ誘引度」の違いに注目!
堆肥の種類によって、ネズミを引き寄せる力が全然違うんです。これを「ネズミ誘引度」と呼んでみましょう。
どの堆肥がネズミにとって魅力的なのか、見ていきます。
まず、生ごみ堆肥。
これはネズミ誘引度が最も高いです。
野菜くずや果物の皮など、ネズミの大好物がたくさん。
「うわー、ごちそうだらけ!」とネズミは大喜び。
だから、生ごみ堆肥を作る時は要注意です。
次に落ち葉堆肥。
これはネズミ誘引度が中程度。
栄養価は生ごみほど高くありませんが、暖かい隠れ家としては最適。
「ここなら冬も快適に過ごせそう」とネズミは考えます。
一方、木材チップ堆肥はネズミ誘引度が低めです。
食べ物としての魅力が少ないため、ネズミはあまり寄ってきません。
「うーん、ここはおいしそうなものがないな」とネズミは素通りするかも。
- 生ごみ堆肥:ネズミ誘引度 高
- 落ち葉堆肥:ネズミ誘引度 中
- 木材チップ堆肥:ネズミ誘引度 低
「じゃあ、木材チップだけで堆肥を作ればいいの?」いいえ、そうともいきません。
栄養バランスの良い堆肥を作るには、様々な材料を混ぜることが大切。
ネズミ対策をしながら、良質な堆肥作りを目指しましょう。
コンポストの温度管理で大切な「55℃〜65℃」の理由
コンポストの温度管理、特に「55℃〜65℃」という範囲がとても大切なんです。なぜこの温度帯が重要なのか、詳しく見ていきましょう。
まず、この温度帯は有害な微生物を退治するのに最適なんです。
病原菌や雑草の種子が死滅する温度なんです。
「やった!厄介者をやっつけられる!」と、堆肥作りをする人にとっては嬉しいポイント。
次に、この温度帯では良い菌がグングン活動するんです。
堆肥を作るのに役立つ微生物たちが、最も活発に働く温度なんです。
「よーし、みんなで頑張ろう!」と、良い菌たちが大活躍。
そして、この温度帯はネズミにとって居心地が悪いんです。
ネズミは20℃〜30℃くらいの温度を好むので、55℃〜65℃は熱すぎて「ヒィー、熱いよ!」と逃げ出してしまいます。
- 有害な微生物を退治できる
- 良い菌が活発に活動する
- ネズミにとって居心地が悪い環境になる
「むむむ、難しそう…」と思うかもしれません。
でも、コツをつかめば意外と簡単。
温度計を使って定期的にチェックし、必要に応じて水を足したり、堆肥をかき混ぜたりしましょう。
こうして適切な温度管理をすることで、良質な堆肥作りとネズミ対策の両方が実現できるんです。
「一石二鳥だね!」そう、まさにその通りなんです。
ネズミ被害を放置すると「堆肥の質低下」が急激に進行!
ネズミ被害を放っておくと、堆肥の質がみるみる悪くなってしまうんです。その恐ろしい進行を、段階を追って見ていきましょう。
まず、ネズミが堆肥を食い荒らすところから始まります。
野菜くずや果物の皮など、栄養価の高いものを選んで食べてしまうんです。
「おいしいものだけいただきま〜す」とネズミは喜んで食べ歩きます。
次に、ネズミのフンや尿が堆肥に混ざります。
これが厄介なんです。
ネズミの排泄物には有害な細菌がいっぱい。
「えっ、せっかくの堆肥が汚染されちゃう?」そう、残念ながらその通りなんです。
さらに、ネズミが堆肥をかき回すことで空気の通りが悪くなります。
堆肥作りに必要な良い菌が活動できなくなってしまうんです。
「あれ?堆肥がうまく発酵しないぞ」という状態に。
こうして、どんどん堆肥の質が落ちていきます。
最悪の場合、使い物にならない堆肥になってしまうことも。
- 栄養バランスの崩れ
- 有害細菌の増殖
- 発酵不良
- 悪臭の発生
- 堆肥の腐敗
「ちょっとくらいネズミがいても…」なんて甘く見ていると、あっという間に堆肥が台無しに。
早めの対策が大切です。
「よし、今すぐネズミ対策を始めよう!」その意気込みで、堆肥の質を守りましょう。
コンポストに「生の肉や魚」を入れるのはやっちゃダメ!
コンポストに生の肉や魚を入れるのは絶対にNGなんです。なぜダメなのか、その理由をじっくり見ていきましょう。
まず、生の肉や魚は腐敗しやすいんです。
堆肥の中で悪臭を放ち始めます。
「うわっ、なんてにおいだ!」と近所の人に迷惑をかけてしまう可能性大。
次に、腐敗した肉や魚は有害な細菌の温床になります。
サルモネラ菌や大腸菌などの危険な細菌が増殖しやすいんです。
「えっ、堆肥が菌だらけに?」そう、健康被害のリスクが高まってしまいます。
さらに、生の肉や魚はネズミを強力に引き寄せるんです。
ネズミにとっては最高のごちそう。
「わーい、ごちそうだ!」とネズミが大集合してしまいます。
そして、肉や魚の脂肪分が多いと、堆肥の分解バランスが崩れることも。
「あれ?堆肥がうまく作れない…」という事態に。
- 悪臭の発生
- 有害細菌の繁殖
- ネズミの大量発生
- 堆肥の質の低下
- 周辺環境の悪化
「じゃあ、肉や魚の残りはどうすればいいの?」という疑問が湧くかもしれません。
これらは自治体の決まりに従って、燃えるゴミとして処理するのが一般的です。
野菜くずや果物の皮、茶がらなど、植物性の生ごみを中心にコンポストを作りましょう。
そうすれば、良質な堆肥ができあがり、ネズミ被害も防げるんです。
「なるほど、肉魚NGで覚えておこう!」そう、それが堆肥作りの基本ルールの一つなんです。
ネズミ対策の要!コンポストの構造設計と周辺環境整備

底に敷く金網は「目開き6ミリ以下」が最適な理由
コンポストの底に敷く金網は、目開き6ミリ以下のものを選びましょう。なぜこのサイズが最適なのか、詳しく見ていきます。
まず、ネズミの体の大きさを考えてみましょう。
一般的なネズミは、頭を通せる穴なら全身が通れてしまうんです。
「えっ、そんな細長いの?」と思うかもしれません。
でも、ネズミの体は驚くほど柔軟なんです。
最小のハツカネズミでも、直径6ミリの穴があれば侵入できてしまいます。
ドブネズミやクマネズミなら、10ミリ程度の穴でも通れる場合があるんです。
だから、6ミリ以下の目開きなら、ほとんどのネズミを締め出せるというわけ。
金網の素材は、ステンレス製か亜鉛メッキ鉄線がおすすめです。
これらは錆びにくく、長持ちするんです。
「せっかく敷いた金網が錆びちゃったら意味ないもんね」そう、耐久性も大切なポイントなんです。
- ハツカネズミ:6ミリの穴を通過可能
- ドブネズミ:10ミリ程度の穴を通過可能
- クマネズミ:10ミリ程度の穴を通過可能
端っこに隙間があると、そこから侵入されちゃいます。
「よーし、完璧に敷き詰めるぞ!」その意気込みで、ネズミの侵入を防ぎましょう。
こうして底に適切な金網を敷くことで、コンポストをネズミの楽園にしてしまう危険性をグッと減らせるんです。
堆肥作りを楽しみながら、ネズミ対策もバッチリ。
一石二鳥ですね!
側面と蓋の「密閉性」vs「通気性」のバランス調整法
コンポストの側面と蓋は、密閉性と通気性のバランスが大切です。このバランスをうまく取ることで、ネズミ対策と堆肥作りの両立ができるんです。
まず、密閉性について考えてみましょう。
側面や蓋に大きな隙間があると、そこからネズミが侵入してしまいます。
「ちょっとした隙間でも、ネズミは入り込んでくるの?」はい、その通りなんです。
ネズミは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
でも、完全に密閉してしまうと今度は通気性の問題が出てきます。
堆肥作りには適度な空気の流れが必要なんです。
「空気が流れないと、堆肥が腐っちゃうの?」そうなんです。
空気が流れないと、良い菌が活動できずに悪い菌が増えてしまうんです。
じゃあ、どうバランスを取ればいいの?
ここがポイントです。
- 側面は基本的に密閉性を重視
- 蓋には小さな通気口を設ける
- 通気口には細かい網を取り付ける
蓋には小さな通気口を複数設けて、そこに目の細かい網を取り付けます。
こうすることで、ネズミの侵入を防ぎながら、適度な空気の流れを確保できるんです。
「うーん、難しそう…」と思うかもしれません。
でも、コツさえつかめば意外と簡単。
市販のコンポストなら、この点を考慮して設計されているものも多いんです。
自作する場合は、このバランスを意識して作ってみてくださいね。
こうして側面と蓋の密閉性と通気性のバランスを調整することで、ネズミを寄せ付けず、かつ良質な堆肥作りができる環境が整うんです。
「よし、バランス良く作ってみよう!」その意気込みで、理想的なコンポストを目指しましょう。
コンポストの設置場所「建物から1メートル以上」離す理由
コンポストは建物から1メートル以上離して設置しましょう。これには重要な理由があるんです。
詳しく見ていきましょう。
まず、ネズミの行動特性を考えてみましょう。
ネズミは壁づたいに移動するのが大好きなんです。
「えっ、なんで?」壁があると背中を守られた感覚になり、安心して移動できるからなんです。
建物のすぐそばにコンポストを置くと、ネズミにとって格好の通り道になってしまいます。
「ここなら安全に移動できるぞ」とネズミは考えるわけです。
さらに、建物に近いとネズミが家の中に侵入するリスクも高まります。
「え、コンポストから家の中に入ってくるの?」そうなんです。
コンポストを足がかりにして、家の壁をよじ登ったり、近くの窓から侵入したりする可能性があるんです。
じゃあ、どうすればいいの?
ここがポイントです。
- 建物から1メートル以上離す
- 周囲に隠れ場所となる物を置かない
- コンポストの周りはできるだけ開けた空間にする
開けた空間だと、ネズミは警戒して近づきにくくなるんです。
「でも、庭が狭いから1メートル離せないよ」という場合もありますよね。
そんな時は、コンポストの周りに砂利を敷いてみましょう。
ザラザラした感触をネズミは嫌がるので、近づきにくくなります。
また、コンポストの周りを定期的に見回るのも効果的です。
人の気配を感じると、ネズミは寄り付きにくくなるんです。
「よし、毎日コンポストをチェックしよう!」その習慣が、ネズミ対策になるんですね。
こうして適切な場所にコンポストを設置することで、ネズミの被害を大幅に減らせるんです。
ちょっとした工夫で、快適な堆肥作りができるようになりますよ。
周囲3メートルの「草刈りと低木剪定」でネズミを寄せ付けない!
コンポストの周囲3メートル以内の草刈りと低木剪定が、実はネズミ対策の強い味方なんです。なぜこれが効果的なのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは身を隠せる場所が大好きです。
草むらや茂みは、ネズミにとって絶好の隠れ家になってしまうんです。
「えっ、そんな小さな草むらでも?」そうなんです。
ネズミにとっては、ちょっとした草むらでも立派な隠れ家になっちゃうんです。
草や低木が生い茂っていると、ネズミは安心してコンポストに近づけます。
「よし、ここなら安全に移動できるぞ」とネズミは考えるわけです。
じゃあ、どうすればいいの?
ここがポイントです。
- コンポストの周囲3メートル以内の草を短く刈る
- 低木は下枝を剪定して、見通しをよくする
- 落ち葉や枯れ枝はこまめに片付ける
- コンポストの周りは砂利や小石を敷く
ネズミは開けた場所を移動するのを嫌がるので、コンポストに近づきにくくなるんです。
「でも、草刈りや剪定って大変そう…」と思うかもしれません。
確かに手間はかかりますが、定期的に行うことで作業時間は短くなっていきます。
月に1回程度の作業で十分効果が出ますよ。
また、この作業には副次的な効果もあるんです。
庭全体が綺麗になり、見通しがよくなることで、ネズミ以外の害虫対策にもなります。
「一石二鳥だね!」そう、まさにその通りなんです。
草刈りや剪定をする際は、安全に気をつけてくださいね。
長袖・長ズボンを着用し、手袋をするのを忘れずに。
「よし、安全第一で作業しよう!」その心がけが大切です。
こうして周囲の環境を整えることで、ネズミを寄せ付けない快適なコンポスト環境が作れるんです。
ちょっとした手入れで、堆肥作りがもっと楽しくなりますよ。
ネズミ対策に効果的な「動体センサー付きLED照明」の活用法
動体センサー付きのLED照明を使うと、ネズミ対策がグッと効果的になるんです。なぜこれが効果的なのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは基本的に夜行性で、暗い場所を好みます。
「暗いところが好きなんだ〜」そう、まさにその通り。
暗闇の中なら、天敵に見つかりにくいと考えているんです。
でも、突然明るくなると、ネズミはびっくりして逃げ出します。
「えっ、そんなに怖がるの?」はい、予期せぬ明るさの変化に、ネズミはとても敏感なんです。
ここで活躍するのが、動体センサー付きのLED照明です。
ネズミが近づいてきたら自動で点灯し、ネズミを驚かせて逃げ出させるんです。
効果的な使い方のポイントは以下の通りです。
- コンポストの周囲に複数設置する
- 照明の高さは地面から30〜50センチ程度に
- 照明の向きはコンポストに向ける
- 明るさは300ルクス以上を選ぶ
- 赤外線センサーのものを選ぶ
高さを低めに設定することで、小さなネズミの動きも確実に捉えられるんです。
「でも、電気代が心配…」という声が聞こえてきそうですね。
でも大丈夫。
LEDは省電力なので、電気代はそれほどかかりません。
それに、ネズミが来ない時は点灯しないので、無駄な電力消費もありません。
さらに、この照明には副次的な効果もあるんです。
夜間の庭を明るくすることで、防犯対策にもなります。
「一石二鳥だね!」そう、まさにその通りなんです。
設置する際は、雨や風に強い屋外用の製品を選びましょう。
「よし、耐久性のあるものを探そう!」その心がけが大切です。
こうして動体センサー付きLED照明を活用することで、ネズミを寄せ付けない環境が作れるんです。
光の力で、コンポストをしっかり守りましょう。
堆肥化を成功させる5つの驚きの裏技!ネズミ撃退法

ミントの植木鉢で「天然の忌避剤」効果を発揮!
ミントの植木鉢を活用すれば、ネズミを自然に寄せ付けない環境が作れます。なぜミントが効果的なのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは鼻がとっても敏感なんです。
「え、そんなに?」と思うかもしれませんが、人間の何百倍もの嗅覚を持っているんです。
そして、ミントの香りはネズミにとって強烈な刺激になるんです。
ミントの香りにはメントールという成分が含まれています。
この成分がネズミの鼻をくすぐり、「うわっ、この臭いは苦手!」とネズミを遠ざけるわけです。
では、どうやってミントを活用すればいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- コンポストの周りに数個のミントの植木鉢を置く
- ミントの葉を乾燥させて、コンポストの中に混ぜる
- ミントオイルを水で薄めて、コンポスト周辺に噴霧する
- ミントティーを作り、冷ましてからコンポストに散布する
「よし、ミントでネズミ撃退だ!」その意気込みで、さっそく試してみましょう。
ミントは種類も豊富です。
ペパーミント、スペアミント、アップルミントなど、好みの香りを選んでみるのも楽しいですよ。
「どの香りが一番効くかな?」と考えるのも、堆肥作りの新しい楽しみになるかもしれません。
ミントは育てやすい植物なので、家庭菜園初心者の方にもおすすめです。
コンポストのネズミ対策をしながら、新鮮なミントの葉も楽しめる。
まさに一石二鳥ですね!
古いCDの反射光で「ネズミを威嚇」する意外な方法
古いCDを使ってネズミを撃退する方法があるんです。意外かもしれませんが、とても効果的なんですよ。
なぜCDが役立つのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは光に敏感な生き物なんです。
特に、急に光る物や動く光に驚きやすい性質があります。
「え、そんなに怖がるの?」と思うかもしれませんが、ネズミにとっては命に関わる問題なんです。
CDの表面は光を強く反射する特性があります。
この反射光が不規則に動くと、ネズミは天敵が近づいてきたと勘違いしてしまうんです。
「ヒエッ、危険だ!」とネズミは逃げ出してしまいます。
では、どうやってCDを活用すればいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- コンポストの周りにCDを吊るす
- CDを細かく砕いて、コンポストの周りに散布する
- CDをコンポストの蓋の内側に貼り付ける
- CDを地面に刺して、風で揺れるようにする
- CDを組み合わせて、風車のようなものを作る
「よし、CDでピカピカ大作戦だ!」その気持ちで、さっそく試してみましょう。
CDを使う利点は、お金をかけずに簡単に実践できることです。
家にある使わなくなったCDを活用できるので、エコにもつながりますね。
「もったいない精神で、ネズミ対策もバッチリ!」一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかもしれません。
ただし、強い日差しの下ではCDの反射光が周囲の目に入る可能性があるので、設置場所には注意が必要です。
近所迷惑にならないよう、気をつけましょうね。
ニンニクの皮で「強力な臭い」のバリアを作る
ニンニクの皮を使ってネズミを撃退する方法があるんです。意外に思えるかもしれませんが、これがとても効果的なんですよ。
なぜニンニクの皮が役立つのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは嗅覚が非常に発達していて、強い匂いを嫌う傾向があります。
特に、ニンニクの香りは彼らにとってとても不快なものなんです。
「え、そんなに嫌いなの?」と思うかもしれませんが、ネズミにとってはまるで化学兵器のような存在なんです。
ニンニクにはアリシンという成分が含まれています。
この成分が強烈な臭いの正体で、ネズミを遠ざける効果があるんです。
「うわっ、この臭いはたまらん!」とネズミは逃げ出してしまうわけです。
では、どうやってニンニクの皮を活用すればいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- ニンニクの皮をコンポストの中に混ぜ込む
- ニンニクの皮を乾燥させて粉にし、コンポストの周りに撒く
- ニンニクの皮を水に浸し、その水をコンポスト周辺に散布する
- ニンニクの皮を小袋に入れて、コンポストの周りに吊るす
- ニンニクの皮とお酢を混ぜて、強力な忌避スプレーを作る
「よし、ニンニクパワーでネズミ撃退だ!」その意気込みで、さっそく試してみましょう。
ニンニクの皮を使う利点は、普段は捨ててしまうものを有効活用できることです。
エコにもつながりますし、コストもかかりません。
「もったいない精神で、ネズミ対策もバッチリ!」一石二鳥の効果があるんです。
ただし、ニンニクの強い臭いが苦手な人もいるので、近所の方への配慮は忘れずに。
風向きや使用量には気をつけましょうね。
ペットボトルの風鈴で「不快な音」を演出!
ペットボトルで手作り風鈴を作って、ネズミを撃退する方法があるんです。ちょっと変わっているかもしれませんが、これがとても効果的なんですよ。
なぜペットボトル風鈴が役立つのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは聴覚が非常に敏感な動物なんです。
特に、突然の音や不規則な音に驚きやすい性質があります。
「え、そんなに音に弱いの?」と思うかもしれませんが、ネズミにとっては生存本能に関わる重要な感覚なんです。
ペットボトル風鈴は、風が吹くたびにカラカラと不規則な音を立てます。
この予測できない音がネズミを不安にさせ、「ここは危険だ!」と感じさせるんです。
では、どうやってペットボトル風鈴を作り、活用すればいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- ペットボトルを輪切りにして、複数のリングを作る
- リングの内側に小石や貝殻を通した紐を通す
- リングを重ねて、コンポストの周りに吊るす
- 風の通り道に複数設置して、音の範囲を広げる
- ボトルの口の部分を残して笛のような音が出るようにする
「よし、リサイクル風鈴でネズミ撃退だ!」その気持ちで、さっそく試してみましょう。
ペットボトル風鈴を使う利点は、身近な材料で簡単に作れることです。
お金をかけずに、しかも環境にやさしいネズミ対策ができるんです。
「エコでおもしろい、一石二鳥のアイデアだね!」まさにその通りです。
ただし、風鈴の音が近所の方の迷惑にならないよう、設置場所や数には気をつけましょう。
夜間は特に注意が必要です。
みんなが気持ちよく過ごせる環境づくりを心がけてくださいね。
唐辛子パウダーで「辛さの壁」を築く効果的な方法
唐辛子パウダーを使ってネズミを撃退する方法があるんです。ちょっと意外かもしれませんが、これがとても効果的なんですよ。
なぜ唐辛子パウダーが役立つのか、詳しく見ていきましょう。
ネズミは嗅覚と味覚が非常に敏感な動物なんです。
特に、刺激的な香りや辛みを強く嫌う傾向があります。
「え、ネズミも辛いのが苦手なの?」と思うかもしれませんが、実はネズミにとって唐辛子の辛さは脅威なんです。
唐辛子に含まれるカプサイシンという成分が、ネズミを寄せ付けない効果を発揮します。
この成分がネズミの鼻や口を刺激して、「うわっ、危険だ!」と感じさせるんです。
では、どうやって唐辛子パウダーを活用すればいいのでしょうか?
ここがポイントです。
- コンポストの周りに唐辛子パウダーを撒く
- 水で薄めた唐辛子パウダーをスプレーボトルで散布する
- 唐辛子パウダーを布袋に入れて、コンポストの中に吊るす
- 唐辛子パウダーと重曹を混ぜて、より効果的な粉を作る
- 唐辛子パウダーを油で溶いて、コンポストの周りに塗る
「よし、辛さパワーでネズミ撃退だ!」その意気込みで、さっそく試してみましょう。
唐辛子パウダーを使う利点は、安価で手に入りやすく、効果が長続きすることです。
雨に濡れても効果が持続するので、屋外のコンポストにも適しています。
「手軽で効果的、いいことづくめだね!」まさにその通りです。
ただし、唐辛子パウダーを扱う際は目や鼻に入らないよう注意が必要です。
ゴム手袋やマスクを着用し、風の強い日は避けましょう。
また、ペットや小さな子供がいる家庭では、触れない場所に使用するなどの配慮が必要です。
安全第一で、楽しくネズミ対策を進めていきましょう。